◯はじめに
こんにちは!
いしだ鍼灸整骨院アシスタントスタッフの亀岡です。
今回は、いつものブログとは少し違う内容になります。
普段は当院からのお知らせやお身体にまつわる情報を中心にお届けしていますが、
先日、私が「四国手話学習会」に参加した日のことを、私自身の学びと感じたことを交えてお話しします。
「え?手話?整骨院と関係ある?」と思われた方もきっとおられますよね。
実は、手話を通じて“相手に伝えること・心を寄せること”について深く考える
とても充実した時間を過ごすことができたんです。
お身体の話題とは少し離れますが、気軽に読んでいただけるとうれしいです。
よろしければ、私が手話を学ぶようになった経緯などもブログにまとめていますので、
過去記事もあわせてご覧ください。
※四国手話学習会は、一社)全国手話通訳問題研究会四国ブロックが主催するイベントです。
四国ろうあ連盟と共同開催されることが多く、四国ブロック全体で手話の普及と福祉向上を目指しています。
◯谷進一さんの手話映画と、心に残る医療・ケアの話
午前中は、手話映画の監督・俳優として活動されている 谷進一さん の上映と講話が行われました。
谷さんは、普段は 訪問看護師 として現場に立ちながら、その経験を “手話映画” という形で表現し続けている方です。
上映された映画には音声がありません。
ですが、表情や手の動きだけで、気持ちがすっと胸に入ってきて、
「手話って本当に豊かな言葉なんだ」と、あたたかい気持ちになりました。
谷さんの手話は、とにかく表現力がすごい。
指先の角度、目線、姿勢、間(ま)の取り方まで、全てが言葉以上の言葉。
その表現の豊かさに、思わず引き込まれました。
講話では、訪問看護の現場で出会った方々とのエピソードを交えながら、
“伝える大変さ” と “理解し合えた瞬間の喜び” について語ってくださいました。
その言葉を聞きながら、
「相手に寄り添うってどういうことだろう?」
と、普段の接し方を振り返るきっかけになりました。

◯手話での交流と、笑顔あふれる学びの時間
午後からは、四国各県から集まった参加者同士で、手話を使った交流がありました。
健聴者・ろう者が一緒になっての活動で、最初は少し緊張気味でしたが、手を動かしているうちに自然と笑顔が増え、
あっという間に距離が縮まりました。
なかでも印象的だったのは、
「グー・チョキ・パー・人さし指」を使った単語出しと文づくりのワーク。
それぞれの手の形からまず連想できる単語を出し、次にその単語をつないで文を作り、
発表するというゲームのような内容で、
「そんな文章になる?!」「面白い!」と笑いが絶えませんでした。
さらに驚いたのは、手話には“地域差=方言”がある こと。
同じ四国でも「えっ!? そんな表現あるの!?」と驚くほど違いがあり、とても新鮮でした。
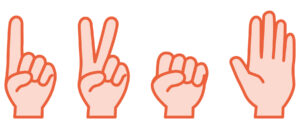
◯各地の手話から感じた、“人とのつながり”
今回の学習会を通して、手話は「言葉」以上に、地域や人の温度を映す文化だと感じました。
単語一つをとっても、その人の表情や手の動きの“癖”に個性が宿る。
まるで、手話がその人自身を映す鏡のようだなと思いました。
「もっと知りたい、もっと伝えたい」
そんな気持ちが自然と湧き上がり、学べば学ぶほど奥深く、ワクワクが止まりません。
言葉が聞こえる・聞こえないに関係なく、
“通じ合いたい” 気持ちがあれば、ちゃんと心はつながる
そんな当たり前のことを、改めて感じた時間でした。
(一人しみじみ…笑)
◯まとめ:仕事にも生きる「伝えること」の大切さ
今回の「四国手話学習会」は、
午前・午後・参加者交流を通して、心に残る学びがたくさんありました。
まず午前中の谷進一さんのお話では、手話映画という新しい表現の世界に触れ、
言葉の音がなくても、人の思いはしっかり届くということを実感しました。
訪問看護師としての経験を手話映画に込め、手や表情、身体の動きを通じて感情を伝える谷さんの姿から、
「伝える」とは言葉だけでなく、相手の心に寄り添う姿勢そのものだと学びました。
午後の手話交流では、健聴者・ろう者が混ざりながら、グループワークや会話を通して
“伝えようとする気持ち”があれば通じ合えることを実感しました。
ゲームのようなワークも多く、笑顔があふれる楽しい雰囲気の中で、コミュニケーションの本質に触れる時間となりました。
また、各地の表現にふれたことで手話にも地域性=文化があるという大きな発見もありました。
同じ単語でも表し方が違ったり、その人らしい癖が見えたりと、手話はただの「動作」ではなく、
地域と人の温度を映す言葉なのだと感じました。
この一日の学びを通して、手話は単なる言語ではなく、人と人を結ぶ“心の架け橋” であることを改めて感じました。
整骨院でも、耳の不自由な方、話すことに不安を感じている方、言葉で伝えるのが苦手な方が来院されます。
今回の経験を通して、そうした方々にも安心して来ていただけるよう心を込めたコミュニケーションを
大切にしたいと、改めて思える一日になりました。
手話も少しずつ勉強しながら、これからも人とのつながりを大切にしていきたいです。
そして、「ここに来てよかった」そう感じていただける場所を目指して、日々の仕事に今回の学びを生かしていきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(いしだ鍼灸整骨院 アシスタントスタッフ亀岡みゆき 監修)
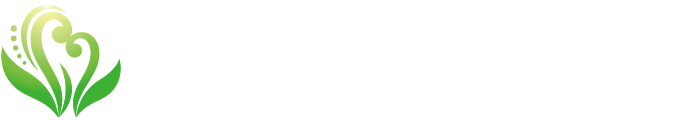






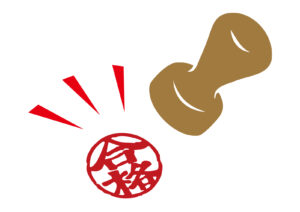

コメント