◯はじめに
こんにちは!
いしだ鍼灸整骨院アシスタントスタッフの亀岡です。
最近、日本各地で地震が増えており、災害への備えや情報の受け取り方が改めて大切だと感じる日々です…
このブログでは普段、院からのお知らせや健康についての情報をお届けしていますが、
今回は少し視点を変えて「手話」と「防災」について書いてみたいと思います。
というのも、私自身の身近な経験と、先日参加した研修が大きなきっかけになったからです。
実は私、現在手話を学んでいます。
きっかけは、生まれつき耳が聞こえない妹の存在です。家族として自然と身振りや表情で伝え合うことが多く、
「もっとしっかり伝えられるようになりたい」
と思ったことが始まりでした。
このあたりの経緯や想いについては、別のブログでご紹介していますので、合わせてご覧ください。
そんな中、先日、西条市で開催された「意思疎通支援防災研修会」に参加してきました。
テーマは「防災〜自分でできること、今からできること〜」
手話や要約筆記を学ぶ仲間が集まり、災害時にどんな支援が必要かを考える、貴重な時間となりました。
普段から「安心して当院に来院してもらうこと」「必要な情報を正しく届けること」を大切に意識しているのですが、
この研修を通じて改めて、
“伝える手段が限られる状況では、それがどれほど困難で、命に直結する問題になるのか”
という事実を目の当たりにました。
このブログでは、研修で学んだことを振り返りながら、災害時に備えて「自分にできること」を
皆さんと一緒に考えていけたらと思います。

◯災害時、聴覚障がい者が直面する困難とは?
災害が起きた時、テレビやスマートフォンから流れる「避難指示」や「緊急情報」。
私たちが当たり前に受け取っている情報の多くは「音声」で伝えられています。
しかし、聴覚障がいのある方には、その音声が届きません。
さらに避難所では、こんな困難があります。
①避難所のアナウンスが聞こえない
②誰かに話しかけられても気づけない
③医療情報や支援物資の配布についての案内が理解できない
④「わからないことがある」と伝える手段がない
⑤ろう者自身が出している音がわからないため、周囲から不信がられることや注意を受ける
ただでさえ不安な中で、情報が得られず孤立してしまう現実。
必要な支援を受けられないまま過ごす方も少なくありません。
特に心が痛んだのは、⑤のように避難所内では避難者同士での誤解が生まれ、
より一層の孤立が生まれるという問題も起こっていることでした。
今回の研修では、こうした「情報のバリア」をどう補い、どう意思疎通を助けるかを、
実際の事例や演習を通して学ぶことができました。

◯支援者としてできること ~手話・要約筆記の力~
研修会では、災害時に手話や要約筆記を活用し、どのように「情報を届ける」か、具体的な方法を学びました。
◎ 避難所でできる対応
• 筆談ボードを活用する
• 災害用伝言カードを事前に配布しておく
• 自治体の防災無線を要約して紙に書き伝える
• 可能な範囲で手話による案内を行う
◎ 意思疎通支援者としての心構え
• 「わからないことは何度でも伝える」姿勢
• 「見守るだけでなく、先回りして情報提供する」意識
• 「一人にしない」ことの大切さ
私はまだ手話も覚えることがたくさんですが、「少しでもできることがあるなら行動しよう」と改めて思えたのは、
仲間と想いを共有できたからだと思います。
「できないから助けられない」ではなく、できる範囲で一歩踏み出すことが命綱になる。
そう実感できた研修でした。
◯防災への備えは、日常の延長線にある
今回の研修では、聴覚障がい者への支援だけでなく、家庭での防災の基本についても学びました。
「防災」と聞くと、非常食や水、防災グッズを揃えるような“特別な準備”を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし本質はもっと身近なところにあります。
研修でも繰り返し語られていたのは、「備えは特別なことではなく、日常の延長にある」 という考え方でした。
*避難場所と避難所の違いを知っておく
似ているようで、実は役割が違うようです。
・避難場所:一時的に身の安全を確保する場所(公園や広場など)
・避難所 : 災害後に生活を送るための施設(学校や公民館など)
いざという時に混乱しないためにも、自分の地域の「避難場所」と「避難所」を家族で確認しておくことが大切ですね。
*持ち出し品は“背負える量”で
• 災害時に持ち出す物は「全部」ではなく、自分が持てる量で考える
• 非常用持ち出し袋は、家族構成や季節を想定してカスタマイズしておく
例えば水は1人1日3Lが目安ですが、すべてを持ち出すのは現実的ではありません。
まずは500mlのペットボトルを数本用意する、という工夫も有効です。
「避難所に行けば安心」ではなく、体力・情報・準備が必要だということを改めて学びました。
実は今回の研修をきっかけに、私自身も防災グッズを改めて見直してみました。
「これで十分だろう」と思っていたのですが、準備不足だったことに気づかされました…。
改めて整える大切さを実感したところです。
*物だけでなく“情報と役割”も備える
防災は物だけではありません。
• 連絡手段はどうするか
• 集合場所はどこか
• 誰が誰を迎えに行くのか
こうした役割を事前に話し合い、紙に書いて貼っておく・LINEグループで共有しておく、
そういった工夫が災害時に役立ちます。
*「何を備えるか」より「誰と備えるか」
そして忘れてはいけないのは、「誰と備えるか」です。
災害は一人で乗り越えるものではありません。
ご近所や職場の仲間と声をかけ合うこと、日常からコミュニケーションをとっておくことが、
非常時の大きな支えになります。

◯おわりに
今回の研修を通じて、「伝わらないこと」が災害時に命に関わる大きな問題になることを実感しました。
特に聴覚障がいのある方々は、避難情報や支援の案内が届きにくく、不安や孤立を抱えやすい現実があります。
そんな中で、手話や要約筆記といった“伝える手段”は橋渡しの役割を果たします。
「完璧でなくても、『筆談や表情、身振りなどできること』を積み重ねることが支援につながる」
研修を通してその大切さを感じました。
また、防災の備えは「特別なこと」ではなく、日々の暮らしの中で少しずつ整えていけるものです。
持ち物だけでなく、心の準備、周囲とのつながり、そして情報へのアンテナもそのひとつ。
誰かと「一緒に考える」ことも、立派な防災だと思います。
私自身、これからも学びを深めながら、必要な情報をわかりやすく届けられるよう努めていきたいです。
そしてこのブログが、「今からできること」を考えるきっかけになれば嬉しく思います。
(いしだ鍼灸整骨院 アシスタントスタッフ 亀岡みゆき 監修)
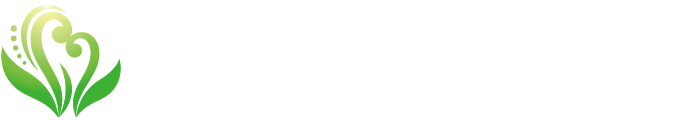






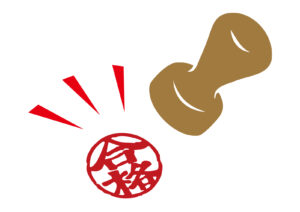

コメント